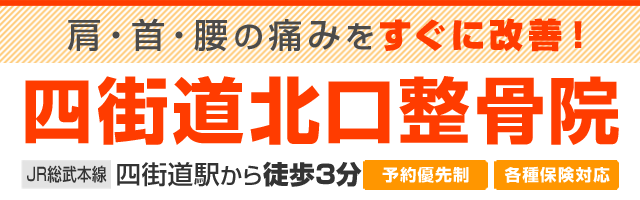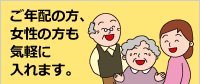眼精疲労


こんなお悩みはありませんか?

長時間デスクワークをしていると目がショボショボしてきてしまい、涙が止まらない。
物がはっきり見えず、ぼやけて見える。
スマホやテレビを見ていると目が疲れ、肩こりまで起こってくる。
画面や物を集中して見ていると頭痛が起こる。
夜にブルーライトを浴びてなかなか眠れない。
鏡で自分の顔を見ると目が充血している。
目が重いと感じる。
目の酷使による倦怠感や、めまい、吐き気がある。
目の奥が痛む。
眼精疲労についてで知っておくべきこと

眼精疲労とは、目を使う作業などを続けることにより、眼痛(目の痛み)、めまい、目の充血などの目の症状や、頭痛、吐き気、倦怠感などの全身症状が出現し、休息や睡眠をとっても十分に回復できない状態をいいます。物を見る際、ピント合わせとして使用する目の中にある筋肉が疲労することによって起こります。
特にスマホやパソコン、テレビなど、自分の目から近い物を見続けると目に負担がかかりやすいため、原因とされている目の中にある筋肉の緊張を緩めることによって症状の軽減が期待できます。(例:遠くにある物を見ることや、目の周りの筋肉をほぐすことで、目の疲れの軽減やリフレッシュにつながります。)
症状の現れ方は?

近年では、パソコンやスマホなどのディスプレイ作業が増加しており、眼精疲労を感じやすいという人も増えています。目を酷使することや、メガネ、コンタクトの度数が合わないことで起こることもあれば、ドライアイ、緑内障、白内障、斜視などの病気が原因となることもあります。さらに、更年期障害、自律神経失調症、虫歯、歯周病、アレルギー性鼻炎、風邪、精神的ストレスなどが原因となる場合もあります。
眼精疲労の症状として、物を見ているとぼやける、かすむ、目が重くなり、ショボショボする、目や目の奥の痛み、涙が出る、充血する、眩しさを感じやすいなどが挙げられます。また、頭痛や肩こり、めまいや吐き気を感じる場合もあります。
その他の原因は?

ドライアイは眼精疲労と深く関係しており、ドライアイの症状が眼精疲労の原因になることがあります。ドライアイとは、目の表面の潤いを保つ涙の量が減少し、涙の成分のバランスが変化することで起こります。
症状としては、目の乾きやゴロゴロとした目の不快感が挙げられます。これらは、テレビ、パソコン、スマホなどの画面を長時間見ていることや、メガネやコンタクトレンズが合っていないこと、また、緑内障や白内障などの全身の健康に問題があることが原因となる場合があります。したがって、ドライアイを予防することは眼精疲労の予防にも繋がります。
ドライアイの具体的な予防方法として、加湿器を使用して湿度を50%〜60%に保つこと、モニターを目の位置より低く設置すること、作業中に意識してまばたきを増やすこと、1時間に1回は画面から目を離し目を休ませ、リラックスする時間を設けることなどが挙げられます。
眼精疲労を放置するとどうなる?

眼精疲労を放置すると、眼疾患の発症リスクが高まることや、頭痛、肩こり、吐き気などの全身の不調が現れることがあります。また、精神的なストレスが増加し、睡眠の質が低下することもあります。さらに、眼精疲労はさまざまな症状と重なりやすく、その場合は、さらに状態が深刻になる可能性があります。
眼精疲労は、目やその周辺の筋肉が緊張することで起こりますが、それを放置することで全身の筋肉にも緊張が伝わり、頭痛や肩こり、めまいや吐き気などの全身の不調に繋がりやすくなります。さらに、自律神経のバランスが乱れ、胃腸や精神面にも影響が出ることもあります。
当院の施術方法について

当院では、最初に指圧にて全身の筋肉の緊張を緩和させた後、眼精疲労に効果が期待できるツボを押し、お身体をリラックスさせた状態にします。その状態で温熱施術として遠赤外線マットをお身体に置かせていただき、全身の筋肉の柔軟性を引き出します。
その後、必要に応じて当院のオーダーメイドメニューである「ドライヘッド矯正」や「全身骨格矯正」などをご提供させていただき、痛みや疲労、辛さの根本から施術させていただきます。そして、患者様に合った期間や頻度をご説明させていただき、患者様に寄り添いながら負担の軽減を図っていきます。
改善していく上でのポイント

筋肉の緊張性による眼精疲労に対しましては、施術を通してしっかりと全身の血流を促進し、正しい骨の位置を維持することで筋肉の柔軟性が生まれます。そのような状態を定着させることによって負担の軽減が期待されます。
ストレス性の眼精疲労に対しましては、施術を通して会話をし、メンタルケアをすることや、ご自身で趣味を楽しむことなど、リラックスできる時間を設けることが負担の軽減につながります。このように施術者と患者様の協力関係を築き上げていくことも1つのポイントです。