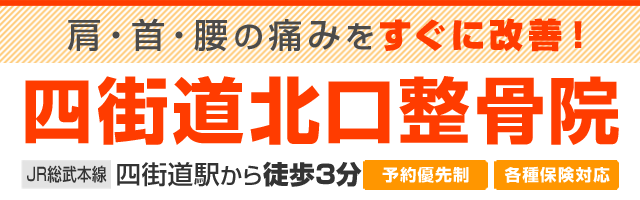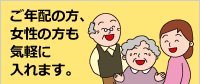肉離れ


こんなお悩みはありませんか?

あなたは運動中や仕事中など日常生活の中でいきなり脚や腕を痛めたりしたことはありませんか?
例えば
ダッシュをして太ももを痛めた
運動中に太ももに痛みが出てきた
ストレッチをすると痛みが出てくる
ぶつけてもいないのに大きな痣のようなものがある
筋肉を押すと強い痛みが出てくる
ここで例に挙げたものは太ももがメインですが、肉離れは腕でもふくらはぎでも発症します。運動不足で最近運動を始めた方や、激しい運動をする学生に多く見られます。
肉離れで知っておくべきこと

先述したように、運動不足の状態から運動を始めた方や、スポーツ系の部活動に参加している学生に肉離れが多く見られます。また、日常生活の中では、点滅し始めた信号を走って渡ろうとした際などに、肉離れが発症しやすいです。
肉離れは、筋肉の柔軟性の低下や筋肉の疲労によって発生する可能性が高まります。筋肉の疲労が抜けきらない状態で運動を続ける「オーバーユース」によっても、リスクが高くなります。
よく発症する部位としては、太ももの裏側にある「ハムストリングス」や、ふくらはぎの「腓腹筋」が挙げられます。また、中年の男性で力仕事をされている方は、上腕二頭筋で肉離れが起きやすくなる場合があります。
症状の現れ方は?

症状の現れ方としては、トレーニングによる筋肉の柔軟性の低下や筋肉の疲労によって発生する場合や、急な動き出し、特定の動きなどによって一発で肉離れが引き起こされる可能性もあります。
肉離れには重症度があり、軽度の場合は筋肉に傷がついたような状態となり、その筋肉を使用すると多少の痛みが生じます。
中度では、「ブチッ」という音や内出血に加え、強い痛みが生じます。
重度の場合は、同じく「ブチッ」という音とともに筋肉が完全に断裂し、受傷後すぐに筋肉に陥没が触知できます。激しい痛みを伴い、内出血の量も多く、広範囲で肌が血液のために紫色になることがあります。
その他の原因は?

運動や急な動作でなることが多いイメージのある肉離れですが、中にはストレッチ中に受傷してしまうこともあります。身体が硬い方がいきなり無理にストレッチを行うと、筋肉の伸縮の許容量の限界を超えてしまい、肉離れにつながることがあります。
また、筋肉の温度を十分に上げておかないと、肉離れを起こしやすくなります。しっかりウォーミングアップを行わずに運動を行うと、肉離れが発生しやすくなります。加えて、気温が低いと筋肉の温度が上がりにくく、肉離れを起こしやすくなります。
このように、運動と肉離れには切っても切れない関係があります。
肉離れを放置するとどうなる?

肉離れは受傷することで内出血が引き起こされる傷害です。そのため、肉離れは後遺症が出やすいスポーツ障害の一つといわれています。
治療を行わずに放置してしまうと、皮下で出血した血液が固まり「血腫(けっしゅ)」や「瘢痕組織(はんこんそしき)」が形成される可能性があります。これにより、しこりやつっぱり感などの違和感が生じやすくなります。そのため、適切なケアを施すことが大切です。
後遺症を放置してしまうと、周囲の筋肉に負担がかかり、肉離れを繰り返しやすくなる場合があります。この状態が一般的に「しこり」として感じられるものです。また、この血腫が筋組織内に残ったまま日常生活や競技に復帰してしまうと、再発のリスクが高まります。
当院の施術方法について

当院では、肉離れの状態についてヒアリングおよび検査を行い、症状を確認した後、最適な施術を行います。
受傷後すぐの場合は、患部に施術を施すと血流が良くなり、再出血し瘢痕が広がる可能性があるため、温熱療法の代わりにアイシングを行います。
肉離れの症状が落ち着き、患部周辺の曲げ伸ばしが可能になってきたら、「筋膜ストレッチ」や「全身骨格矯正」などを行い、筋肉の柔軟性および骨格の位置を正しい位置に戻すことで、身体の歪みを取り除き、身体にかかる負荷を軽減させます。
さらに、「楽トレ」を使用した電気による筋力強化により、負傷しにくい筋肉を作ります。
改善していく上でのポイント

先述したように、肉離れは筋肉の柔軟性の低下や筋肉の疲労などが原因で発生します。さらに、筋肉の量のアンバランスが原因で起こる場合もあります。そのため、肉離れを軽減していく上で重要となるのは、ストレッチ・筋力トレーニング・休息の3つです。
1つ目の柔軟性については、かたいゴムと柔らかいゴムのどちらが引っ張った際にちぎれやすいかをイメージしていただけると分かりやすいです。柔らかいゴムのほうが良く伸び、耐久性もあります。筋肉も同じで、柔軟性が高いほど肉離れを起こしにくくなります。
2つ目の筋量のアンバランスについては、筋力トレーニングをする際に片方の作用だけでなく、反対の作用を持つ筋肉もバランスよくトレーニングすることが大切です。片側だけを過度に強化すると、反対側の筋肉が出力で負けてしまい、無理な動きを強いられることで肉離れのリスクが高まります。
3つ目の休息については、大会が近いなどの理由で練習に必死になるお気持ちは理解できますが、痛みを我慢せず休息を取ることが大切です。筋肉が疲労すると、肉離れだけでなく他のケガのリスクも高まります。身体に違和感を感じた際は、しっかりと休息を取りましょう。また、練習後に疲労した筋肉に対しては、アイシングなどを行い適切なケアをすることをおすすめします。